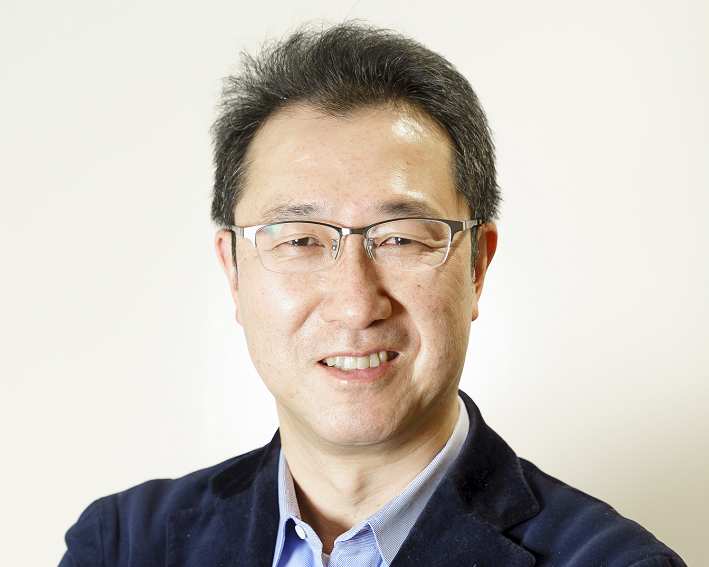#06 ハードルしかなかった株式上場への道。 評価の本質はビジネスモデルと成長性

2014年6月27日、レアジョブは東証マザーズに株式上場した。
前途洋々…とは言えないものの、企業として一段高いレベルに上がる節目を迎えることができた。
IPOは、2008年にグローバル・ブレイン株式会社の資金調達を受けた時点から描いていた未来のひとつ。
また、業界や企業に対する信頼を可視化する手立てとしての意味も大きかった。
オンライン英会話サービス業界そのものが伸びていたとはいえ、事業者の多くはベンチャー企業。
2010年代に入り、ちょうど大手競合他社が台頭しだした時期でもあった。
法人研修や教育機関向けの事業拡大には企業としての信頼が欠かせない。
オンライン英会話トップの“上場企業”になることは、さらなる成長の切り札だった。
さらに、レアジョブのIPOが叶えば、日本の英語教育の常識や先入観を打ち破れるとの期待もあった。
かつて、英語教育には高額な受講料が必須というマイナスイメージがつきまとっていた。
ネイティブ信仰、英語教育=オフラインという常識、文法偏重の教育カリキュラム。
打破すべき壁は少なくなかった。
上場企業の誕生は、オンライン英会話業界そのものの認知度や信頼向上につながるはずだと見込んでいた。
上場のベネフィットは多い。
とはいえ、IPOの準備を始めても、実際に証券会社の審査まで行き着く企業は約3割と言われている。
東証の審査に至っては、1割に満たない。
その理由を一言で表すならば「大変だから」に尽きる。
予実管理や業績開示などの運営をすべて自社で行うために、人員もコストも労力も必要となるのだから。
ならば、なぜレアジョブはこの狭き門をくぐり、株式上場にこぎつけられたのか。
人員も資金も潤沢に揃っていたから?
IPOの準備がスムーズに進んだから?
事実はまったくの逆である。
藤田がレアジョブに入社したとき、IPO推進の要となるはずの管理部門スタッフは2名しかいなかった。
しかも当時の責任者が退職してしまい、いわば最初から窮地に立たされていた。
そこに起こったのが、2012年の受講者の個人情報流出が疑われる事故(インシデント)である。
サービスを全停止して対策を講じ、組織やセキュリティ対策を抜本的に作り直した。
売上は立たないが、会員の方への返金やフィリピン人講師に報酬の前貸しのための資金は必要だ。
事業継続ができなければIPOなど叶うはずもなく、急場しのぎの銀行借り入れで資金調達を行った。
また、IPOは担当者だけで進めるものではない。
全社的にその意義を理解し、新しいやり方を受け入れていくステップが不可欠となる。
そもそも、ベンチャー企業にとってIPOは大きな成長であると同時に、一歩間違えれば取り返しのつかない致命傷を負うというリスクもある。
制度や体制の整備は、自由度の高さやスピーディな判断に対するブレーキとしての機能を意味するからだ。
たとえば、口頭確認でよかった稟議の証跡を明確に残すことが求められる。
「窮屈になった」と感じれば士気が下がり、社内の雰囲気やカルチャーさえ変化するかもしれない。
IPOのプロセスが“ベンチャー殺し”になった例を、藤田はよく知っていた。
上場すれば、働き方もスタンスも従来とは一変する。なぜそうなるのか、スタッフはどうすればよいのか。
一人ひとりが腹の底から納得できるように、経営陣は半期ごとの事業戦略発表会などで全社に説いた。
グレーゾーンになりがちな残業代についても、過去2年分までさかのぼり、退職者にも全員と連絡を取って全額支払った。

IPO準備の一環として、2013年5月に企業・サービスロゴを刷新。
「英会話教育を起点に、社会課題を解決し変革を起こす上場企業へ」との想いを込めて
インシデントを乗り越え、社内体制の整備も進めつつ、さらにIPOへのアクセルを踏んでいこうと思った矢先の2012年末。
今度はアベノミクスによって急激な円安に転じ、再びピンチに見舞われた。
「レアジョブ英会話」は、会員の方から日本円でサービス利用料をいただき、フィリピン人講師にペソで給与を支払う。
つまり円安は原価率圧迫の原因となるわけで、一難去ってまた一難である。
原価率上昇を吸収するため、コスト削減などに苦慮しつつ価格改定も実施した。
為替リスクも何とかクリアし、いよいよ東証に上場申請だ…という2014年2月、今度はフィリピン側で税制問題が発覚する。
フィリピン国税局との争点はいくつかあったが、たとえば取引通貨を円建てにしていたことで、課税に関する理解の相違が生じていた。
さらに、当時の「レアジョブ英会話」の講師はIC-HBT(Independent Contractor/ Home Based Tutor:業務委託の在宅勤務講師)のみだったが、講師を一般人とみなすかプロフェッショナルとしてみなすかによって源泉税が変化する。
こうした税制問題もすべてクリアにするために、過去3年分の監査をたった1カ月ですべて洗い直した。
無事に上場を果たすためには、一点のくもりも残さず整理しなくてはならない。
2014年6月の株主総会までに、決算期をまたいで上場できるギリギリの日時を逆算してスケジュールをはじき出し、監査法人の協力もあおぎながら何とか東証への申請を間に合わせた。
これらの対応の結果、レアジョブは史上初と言ってもいいほどの“直前期債務超過”で、超スモールIPOとなったわけだが。
IPOのための準備は、改めてグループビジョンやサービスミッション実現に向けた意志や姿勢を整理し、言語化する契機となった。
ここまでのストーリーはいずれも、レアジョブが株式上場までにたどった足跡、数々のハードルを乗り越えたチャレンジの軌跡。
しかし、上場できた本質的な理由は、特徴的なビジネスモデルと成長への期待にあった。
2014年当時、オンライン英会話事業者に上場企業はなかった。
少子化の日本では教育産業自体が投資されにくいが、レアジョブは「クラウドソーシング」「C2Cのマッチングビジネス」「日本と海外を結ぶ」など、“IT事業者”としての性格が強い。
一方、株式市場において“教育事業者”は、事業の合理化やスケールアップが難しいとみなされやすい。想いの強さがビジネスの枷になることが多いからだ。
この点で、レアジョブは教育事業者と一線を画する企業、異なる分野で成長が期待される存在として認知されていた、と藤田は考えている。
グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”にも、そのスタンスは反映されている。
レアジョブは「どこにいても、誰に対してもチャンスを提供する会社」で、その手段のひとつとして英語教育を選んだ、というロジックだ。
「英語教育の質を高めていく努力」と「ビジネスモデルの本質」は、異なる文脈で共存している。
東証マザーズ市場は、成長が期待されるベンチャー企業を中心とした株式市場。
どんなに利益を出していても、成長性が期待できなければ上場承認は下りない。
会社の経営体制が整っていることはもちろん、ビジネスモデル、社会課題の解決なども上場承認の対象として評価される。
英語教育市場における成長性への期待と、日本とフィリピンを結びつけて価値を生むビジネスモデル、そして経営体制が揃ったからこそ、レアジョブは上場を果たせたのである。
山あり谷ありの道のりを経て上場承認が下りたとき、思わず涙してしまった中村の胸の内には、さまざまな感情があふれていた。
後に、中村は「当時のCTOが泣いていて、スタッフからのメッセージ動画も流れてくると『みんなでがんばってきたんだな…本当にありがとう』と感極ってしまった」と、このときのことを述懐している。

とはいえ、株式上場は決してゴールではなく、さらなる成長へと続く通過点。
一段高いステージのスタートラインに立ち、先を見据え、また走り続けていくだけなのだった。
もちろん、この後に株価停滞で長らく苦戦する未来など知る由もない。
仮に知っていたとしても、真摯に向き合い対処するのみと考えるだけだろう。
地に足をつけ、等身大のチャレンジを地道に続けていくのが、レアジョブなのだから。

証券コード「6096」をかたどったお祝いのケーキ